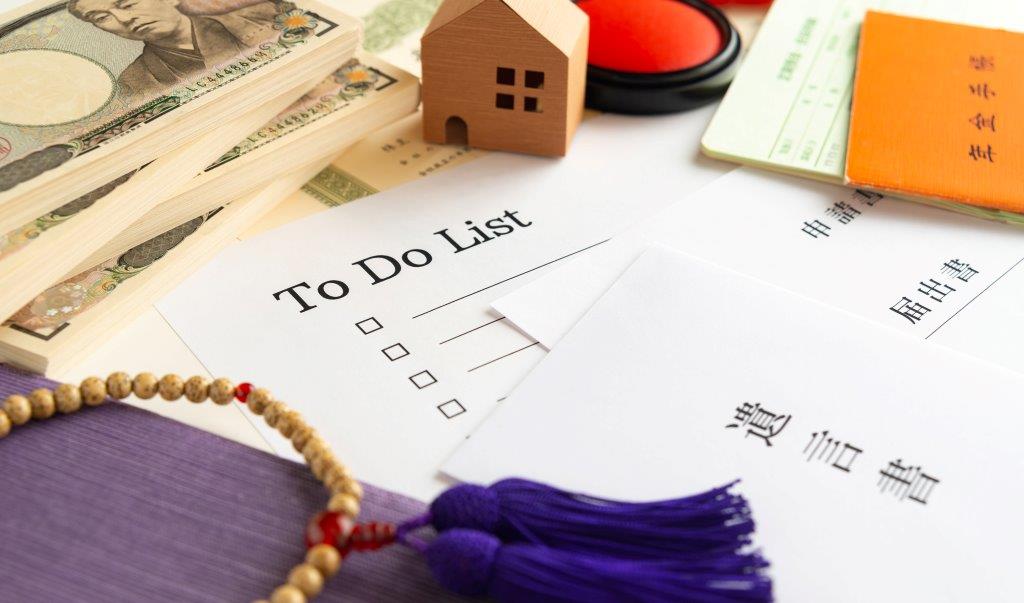特別受益に時効があるか(民法改正との関係)
民法改正で、特別受益の主張に時効ができたのですか。としばしば聞かれます。
この点、一面ではそうだともいえますし、そうでないとも言えます。
民法改正で、限定した場面では、時効の問題になることが、出てきました。
その辺り解説します。
改正民法の条文
改正民法では
第1044条
1 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
1 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
とされています。
条文解説
ここで注目すべきは1044条の3項です。
「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」とありますが、これは特別受益である相続人への生前贈与を指します。
この規定で、遺留分減殺請求で戻せる特別受益の規定は10年以内とされました。
あくまで規定自体は、遺留分減殺請求の中で、特別受益に当たる金銭を持ち戻す際の主張です。
遺留分減殺請求の中で問題にする場合とは、
・遺言があってそこでの遺留侵害を問題にするにあたり、特別受益が関係してくる場合とか
・生前贈与の額が大きすぎて遺留分を侵害しており、通常の特別受益の検討を超えて生前贈与を返すように遺留分減殺請求する場合など
です。
特別受益の時効について
それ以外の特別受益についても、時効の定めの規定が施工されました。以下の通りです。
民法(期間経過後の遺産の分割における相続分)第九百四条の三
前三条の規定(*特別受益と寄与分の規定です(弁護士追記))は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
以上の通り、特別受益の主張は10年とされました。
また、同時に寄与分の時効も10年とされています。